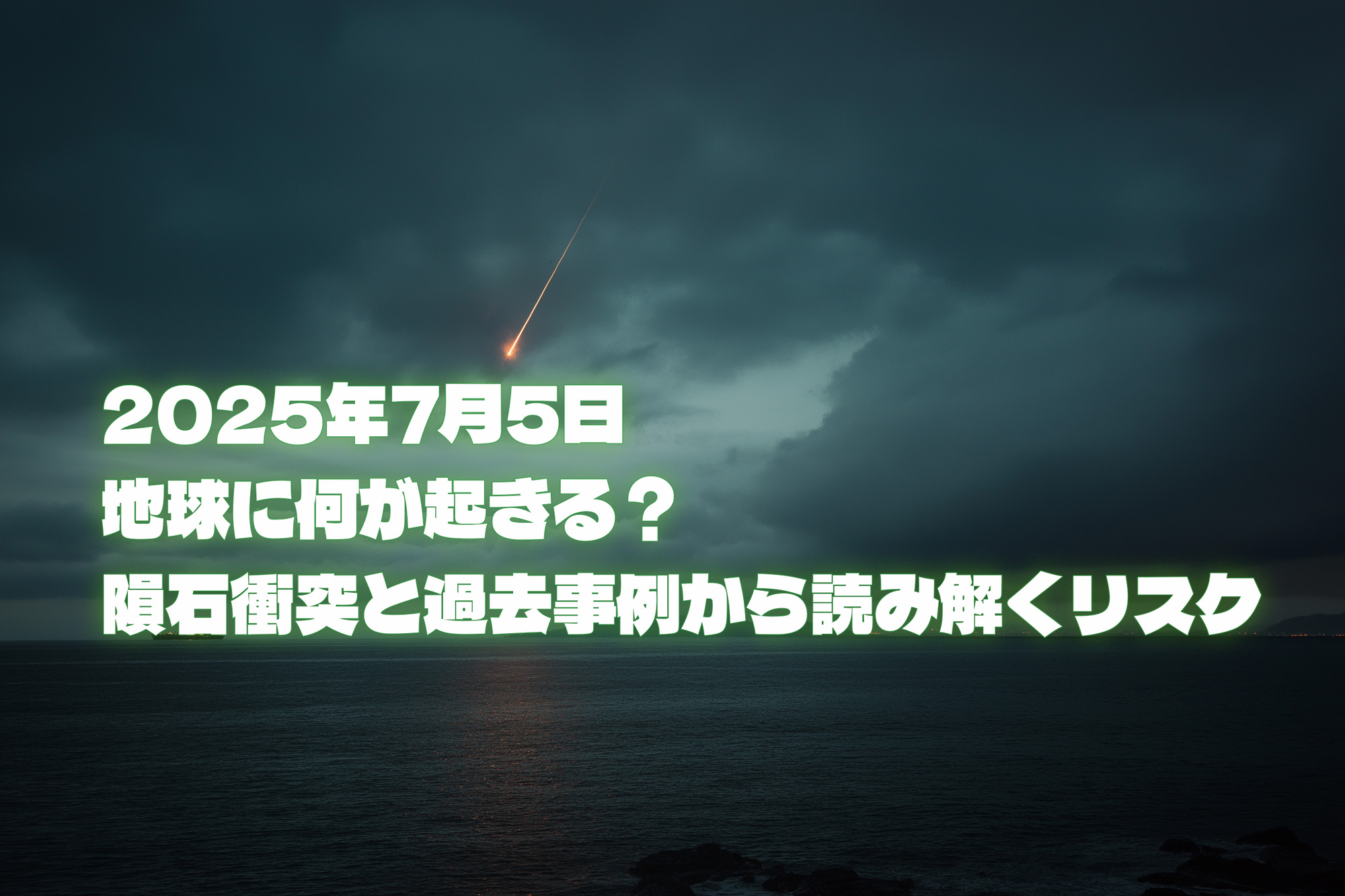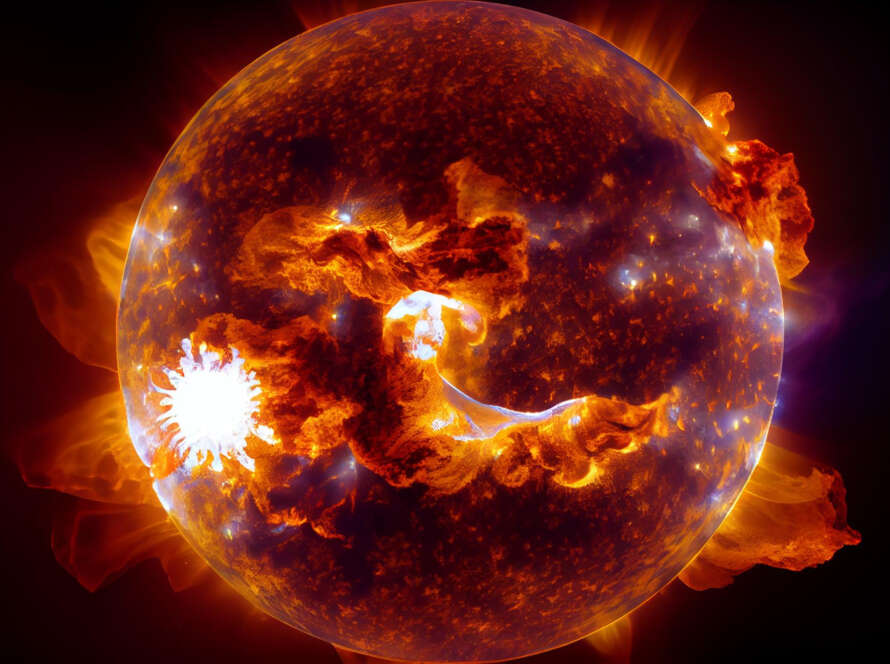「2025年7月5日」という日付が、ここ最近ひときわ注目を集めています。
きっかけは、漫画家・たつき諒さんがかつて描いた予知夢に基づく言葉——「富士山が海に沈む」。
この衝撃的なビジョンは、その日付とともに再び多くの人々の関心を呼び起こしました。
予言の内容だけでなく、この日に“隕石が海に落下する”のではないかという説まで広がっています。
その根拠として、理論物理学者の保江邦夫氏が独自に導き出した計算式があるとも報じられていますが、科学的な詳細までは公に明示されているわけではありません。
一方、NASAやESAといった宇宙機関は、日々地球近傍天体(NEO)の軌道を追跡しており、2025年7月5日に地球と明確に衝突することが予想されている天体は、現時点で報告されていません。
ただし、仮に直径数十メートル級の小惑星が接近していたとしても、それが確実に発見されているとは限らないという点も、宇宙の広大さを思えば理解できる話です。
ここで重要なのは、予言の正否を議論することではなく、「過去に実際に起きた隕石衝突事例から、現在のリスクをどのように評価すべきか」を知ることです。
本記事では、歴史的事例と最新の科学的知見をベースに、現実的なリスクを冷静に見つめていきます。
CONTENTS
過去の隕石衝突事例 地球に刻まれた“衝突の記憶”
隕石衝突は、私たちが思っている以上に「頻繁に起きている自然現象」です。
特に地球規模での被害をもたらすものは少ないにしても、小〜中規模の衝突は数年に一度、大気圏内では毎年複数回確認されています。
ここでは、地球の歴史において特に重要とされる隕石衝突の実例を見ていきましょう。
● チクシュルーブ衝突事件(約6600万年前)
地質学的なスケールで見て、最も破壊的な隕石衝突といえば「チクシュルーブ・インパクト」です。
今から約6600万年前、現在のメキシコ・ユカタン半島に直径10kmとされる巨大な小惑星が衝突しました。
このとき形成されたのが「チクシュルーブ・クレーター」。
その直径は180kmにおよび、地球の地殻構造を激しく変化させるほどの衝撃だったとされています。
衝突のエネルギーは、広島型原爆の数億倍とも言われます。
この事象は地球史上最も有名な大量絶滅の引き金となり、恐竜を含む地球上の生物種の約75%が絶滅したと考えられています。
隕石衝突が「地球の進化そのものを変えうる力」を持つことを、この事件は如実に物語っています。
● ツングースカ大爆発(1908年)
時を大きく進めて、20世紀初頭のロシア・シベリア。
1908年6月30日、上空で突如として大爆発が起き、約2000平方キロメートルに及ぶ森林地帯がなぎ倒されました。
爆発のエネルギーはTNT換算で15メガトン。
これはツァーリ・ボンバ(人類最大の水爆)の約1/4の威力に匹敵します。
この爆発は、地表にクレーターを残していないことから「空中爆発」だったとされており、直径50〜60m程度の隕石、あるいは彗星の一部が大気中で爆発したと見られています。
ツングースカ事件の興味深い点は、その規模にも関わらず、もし落下地点が都市部だったならば、数十万人単位の被害が出ていた可能性があるという点です。
人の少ないシベリアの僻地だったため、大惨事には至らなかったという“偶然”の上に成り立った回避劇だったと言えるでしょう。
● チェリャビンスク隕石(2013年)
21世紀の我々が「現代における隕石衝突の現実」を知る上で、最も鮮烈な例がこのチェリャビンスク隕石です。
2013年2月15日、ロシア南部のチェリャビンスク州上空に突如現れた火球が、大気圏に突入し空中で爆発しました。
直径約20m、質量1万トン、速度は秒速19km。
この爆発は広島型原爆の約30倍のエネルギーを放出したとされます。
空中での衝撃波により、街中の建物の窓ガラスが吹き飛び、1500人以上が負傷。
防犯カメラやダッシュボードカメラによってその一部始終が記録されたため、世界中で報道されました。
この事例からわかるのは、比較的小さな隕石でも、空中で爆発することで都市に甚大な被害をもたらし得るという事実です。
そして、チェリャビンスクの隕石は「事前に観測されていなかった」こともまた、現代の監視体制における盲点を浮き彫りにしました。
現代の監視体制と「2025年7月5日」への視線
前章までで確認した通り、隕石衝突は決して空想の話ではなく、実際に過去に繰り返し起きてきた出来事です。
では、私たちが暮らすこの「今」の地球は、どのようにしてそれらのリスクと向き合っているのでしょうか。
そして話題の「2025年7月5日」という日付に関して、科学的にはどう評価されているのでしょうか。
地球近傍天体(NEO)の監視体制
現在、NASAやESA(欧州宇宙機関)をはじめとする複数の宇宙機関は、「地球近傍天体(Near-Earth Objects)」の軌道追跡を日々続けています。
特にNASAは「センチネル計画」や「DARTミッション」などを通して、地球に接近する可能性のある天体のデータを蓄積・分析しています。
これまでに発見されたNEOの数は数万にのぼり、その中でも地球に深刻な影響を与え得るサイズ(約140m以上)の天体に対しては特に重点的な監視が行われています。
また、小規模な天体も望遠鏡ネットワークを通じて定期的に観測され、アメリカ・アリゾナ州のカタリナスカイサーベイ、ハワイのパンスターズなどが主な観測拠点となっています。
2025年7月5日をめぐる議論
「2025年7月5日」、この日付に特別な意味を持たせているのは、漫画家・たつき諒さんがかつて描いた“夢による予知”に基づいています。
彼女の著書やイラストの中では、「日本列島の南に位置する太平洋の水が盛り上がる」という現象が描かれており、それによって東日本大震災時の約3倍規模の津波が日本を襲うとされています。
具体的な原因については明示されていませんが、ネット上ではその津波の引き金として「隕石の海上落下」が関連づけられるケースも見られます。
さらに、理論物理学者の保江邦夫氏もこの日を「重力変動と隕石衝突のタイミングが重なる可能性がある」と指摘しており、一部で物理学的仮説も飛び交っています。
ただし、これらの主張には現時点で検証可能な天体観測データが伴っているわけではありません。
科学的な評価と観測のギャップ
NASAの公式なNEO監視データベースにおいて、2025年7月5日に衝突の危険性が指摘されている小惑星は存在していません。
国際天文学連合(IAU)やジェット推進研究所(JPL)も、当該日付に特化した警報や注意喚起は行っていないのが現状です。
しかし、2013年のチェリャビンスク隕石のように「事前に発見されていなかった天体」が突如として地球の空に現れる可能性は、完全には排除できません。
特に直径20m以下の小型天体は、暗く観測が難しいため、既存の監視体制をすり抜けることがあります。
したがって、科学的には「衝突の予見はされていない」が、「盲点がないわけではない」というのが現実的な認識です。
隕石衝突リスクとその特性:その“可能性”は何を意味するのか
これまで見てきたように、地球は決して“安全地帯”ではなく、宇宙という広大な空間の中で、他の天体と常に隣り合わせの存在です。
特に小惑星や隕石の衝突は、その確率こそ低いものの、「起きたときの影響」が極めて大きいという特性を持ちます。
衝突確率は“非常に低いがゼロではない”
NASAのNEO(地球近傍天体)観測によれば、直径1km級の天体が地球に衝突する確率は約50万年に1回とされています。
これはかなり稀な現象に思えますが、地球の長い歴史を考えれば「何度も繰り返されてきた」事実です。
一方で、直径10m以下の隕石については話が別です。
これらは年間数回〜十数回の頻度で地球の大気圏に突入しており、その多くは燃え尽きて地上まで到達しません。
しかし、2013年のチェリャビンスク隕石のように、直径20m級でも甚大な人的被害を出す可能性があることは記憶に新しいところです。
したがって、重要なのは「巨大隕石」ばかりに目を向けるのではなく、「小型でも都市部に落下した場合のリスク」にも目を向ける必要があるという点です。
「確率×被害規模」=衝突リスク
リスク評価の基本は、「発生確率」と「発生した場合の影響」の掛け算です。
例えば、地震や台風は頻繁に起きる自然災害であり、そのために多くの備えが社会的に整えられています。
しかし、隕石衝突は「100年に1度以下」の頻度しかないため、備えも議論も後回しにされがちです。
けれども、仮に直径100m級の隕石が海上に落下した場合、周囲数百キロに津波が発生するという試算もあり、その影響は国家単位を超える規模になり得ます。
つまり、「確率が低いから無視していい」というわけではなく、「起きたらどうなるか」という視点とセットで考えるべきもの。
それが隕石衝突の持つ“非対称リスク”の本質です。
見つけにくく、予測しづらい
また、隕石衝突の厄介なところは、「発見されていない天体」の数が膨大であるという点です。
NASAによると、地球の軌道に近い位置を通過するNEOのうち、直径140m以上の天体は約2万個。
そのうち半数以上が未発見、あるいは軌道が正確に追跡されていないとされています。
さらに、天体が地球の夜側(太陽と反対側)から接近してくる場合、反射光がほとんど得られないため、望遠鏡による観測も困難になります。
この“観測の死角”が、衝突リスクの不可視性を高めている要因でもあります。
衝突は「場所」がすべてを決める
衝突の影響は、落下する天体のサイズや速度もさることながら、「どこに落ちるか」で劇的に変わります。
- 陸地の都市部に落ちれば、人的・経済的被害は甚大。
- 海洋上に落ちれば、大規模な津波が発生する可能性。
- 極地や砂漠地帯ならば、被害は最小限に抑えられることも。
このように、同じサイズの天体でも、落下場所によって“運命が分かれる”というのも隕石衝突の重要な特徴です。
終わりに:宇宙からの訪問者に「備える」のではなく「知っておく」
ここで述べてきたように、隕石衝突のリスクとは、「起こる確率が低いから無視していい」ものではありません。
それはむしろ、「起きてからでは間に合わない」類の事象であり、理解と関心をもつこと自体が、未来の判断にとって重要な意味を持ちます。
予言や説が注目される一方で、それを鵜呑みにせず、過去の事実と科学的な観測から冷静に状況を把握すること。
それが私たちにできる“科学的リスク認識”の第一歩ではないでしょうか。
YouTubeで配信しています
チャンネル登録 よろしくお願いします ⇓⇓⇓⇓⇓